文章教室スコーレ
静岡県浜松市中区
元城町 219-16
TEL: 053-456-3770
FAX: 053-456-3795
|
 |
 |
 |
 |
 |
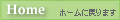 |
 | |

本当の自分になれた理由(わけ)岩瀬郁乃 (高3) パリッとした袴に袖を通し、鉢巻をきつく締める。見慣れた青空も今日は自分の味方のようだ。仕上げに真っ白い手袋をはめれば、「もう一人の自分」の完成だ。全身に響く太鼓の音と、吹奏楽が演奏する「タッチ」が調和し、生徒がヒートアップしてゆく。そう、この感覚。岩瀬郁乃が「わたし」から「ぼく」に変われる唯一の時間だ。「ぼく」は今、高校生の応援団の一人。そして、必死に選手達に「エール」を送っている。
「学校休んでいい?」。中学一年の夏、私は母に告げた。私はその頃イジメを受けていた。キッカケは、クラスが担任へ送った「葬式音頭」。担任の目の前で「おっ葬式、おっ葬式」と手拍子と共に掛け声をするクラスメート。先生はうつむき、無表情で立っている。「やめろよ!」。気づくと私は叫んでいた。教室は静まり返り、先生は飛び出して行った。
次の日から担任は休職した。そして、私はイジメの対象になったのだ。机の落書きから始まって、毎日のように「バカ」「死ね」と言われた。それでも学校に通い続けたのは、その時放送委員だった私に、アナウンスという仕事があったからだ。「皆さん、おはようございます。今日も一日元気に過ごしましょう」。私にとって朝、昼、掃除の時間という一日三回の放送は、唯一の安らぎだった。
「学校休んでいい?」。私の言葉に母はふと笑った。私はその日から不登校になった。
中学二年の秋。母の「クリニックに行こう」の言葉に何の不審も持たず、病院へ行った。先生は私の目を見ながら、「(心に)大きな傷がついていますね」と言った。
クリニックのデイ・ケアで私は、色々な人達と出会った。嫌なことがあると奇声を発してしまう学生。親の虐待で苦しんでいる子供など。形はそれぞれ違うけど、誰もが傷ついていた。デイ・ケアで、私はよく一人でいた。
ある日図書室で本を読んでいた私に、一人の青年が話しかけてきた。彼の名前は「ナリ」。ナリは、いつもどこか遠くを見ているようだった。「レディー・ファ?スト」。それが彼の口癖だった。部屋に入る際、重い荷物を運ばなければいけない時など。気がつくといつも私の傍らに、彼は立っていた。そして「レディ─・ファ─スト」と静かに声を掛けた。私は彼の「レディー・ファースト」を聞くたびに、ある思いを抱いた。どうして彼は、イジメられても人に優しくできるのだろう。私は人を恐れ、私をイジメた人を憎んでさえいるのに。いつしか私は、ナリの「レディー・ファースト」という言葉の奥に隠されているものを探っていた。そしてナリは人からの「優しさ」を求め、「レディー・ファースト」と言うのだという答えに行き着いた。そのようにして彼は、憎しみや恐怖に向き合っていたのだ。そう考えたら、逃げてばかりいる自分が情けなく思えた。ナリ達との生活の中で、私の心は静かになっていった。気持ちが落ち着くと同時に、私の中に沸き起こるものがあった。もっと強くなりたい。そういう思いだった。今思うと恥ずかしいが、(イジメをした人たちを見返してやりたい)という気持ちも含まれていた。まだその時は、ナリの行動の意味が私に浸透していなかったのだ。私は、学びたい気持ちを母に伝えた。
「家庭教師の先生に教えてもらうのはどう?」。それが母の提案だった。
「こんちわぁ」。F先生の第一印象は最悪だった。彼は髪の毛の色からして少し不良っぽく、どこか軽い感じに見えた。
週に二回のペースで先生はやってきた。「豚のワクチンの研究で、誤って自分に打っちゃったよ」授業の前に、彼はまず自分のことを話した。「車に撥ねられて、着いた場所が病院の前でさぁ。友人に電話したら、俺じゃなくてバイクの心配されちゃったよ」。先生は、どこか遠い世界に住んでいるような人だった。私は彼のペースに吸い込まれていった。「えー、こんなに宿題やるの?」と文句の一つも言おうものなら、<地獄のでこピン>が瞬時に飛んでくる。先生との時間は楽しかった。だが彼は意識的にか自分の過去を語ろうとしなかった。どんなに私が聞いても。
そんな思いのある日、私は言った。「今までみんなに元気づけられたから、今度は私がみんなを元気にしてあげられたらなあ。でも、人の気持ちがよく分からないんだ」。先生は笑いながら、「郁乃ちゃんなら大丈夫だよ。俺でさえ分かるようになったんだから」。それから真顔で「郁乃ちゃんってさぁ、石がたくさんあるところでは普通に歩けるのに、その石をどけてやると、とにかくこけっぱなしだよね」と話をつなげた。上手い例えだと私は内心、拍手していた。
この頃、私はデイ・ケアを卒業し、遠く離れた学校に転校していた。クリニックを去る時、私が感じたことがあった。それは、通い始めた頃より、もっとたくさんの患者でクリニックが溢れていたことだ。たった半年の間なのに、心の問題でそこを訪れる人が増えたのだった。
子供は、イジメる子もイジメられる子も、なぜそうなってしまうのか理解できない。私はナリやF先生と関わりながらそのことを学べた。そしてその背後には、大人の作った社会の歪みがあることを感じていた。その社会は、支えることやエールを送ることよりも、人から心を奪うような在り方をしている。「絶対、負けるか!」。私は決意した。そして、「負けない」と思う気持ちは、「人の痛みを知る」という方向に向かった。
転校先で再び私はイジメに遭った。私は再びF先生にそのことを話した。彼は当たり前のように「その子達もきっと辛いことがあるんだよ。それを発散する場所がないから郁乃ちゃんに当たってるんじゃないかなぁ。その子達も弱い人間だってことだよ」と言った。この言葉を聞いた時、私は不思議と安心し、そこに自分の過去を語らない彼の姿を見つけた。先生の過去と私の何かが重なった。
最近の若者は、将来の夢が希薄だと誰かが言っていた。「違う」と私は思った。それは、若者に希望や夢を与える社会が無いからなのに、と。以前、新聞ではニートの数が推定八十万人と報道していた。テレビで放送された、部屋に一人で閉じこもり、ただただゲームにのめり込んでいる青年が思い出された。その時私には、彼の心が見えた。彼はゲームの画面の中で、一人の戦士を操作しているのだ。まるでそれは、大きな不安を消そうと必死に刀を振っている彼自身であるかのように。
人は一人では生きられない。彼も画面の向こうに、寄り添う人を求めているのだろう。
私はいつの間にか、生活の中で何かあると、F先生とナリを思い浮かべていた。そして、私はいつしか、臨床心理士を目指すようになっていた。その夢に火を灯したのはF先生の言葉やナリの「レディー・ファースト」だった。彼らのささやかだが、強い「エールする心」だった。それを理解できるようになって、「誰かを見返す」という思いが消えた。
高校に入学して、転校前の中学でイジメの中心だった子が、同じクラスにいた。F先生の言葉がふと蘇る。「郁乃ちゃんなら、もう大丈夫だよ」。私はもう動じなかった。
高校一年の夏。私は学校の野球部の応援に行った。その時初めて、袴を着た応援団に出会った。ガムシャラに応援している彼らの姿を見て、私も一緒に応援したいと感じた。
高校二年の夏。私は炎天下の下、袴を着て立っていた。ここにいる自分は中学の時のように、恐怖から逃げることしか考えなかった自分ではない。私は色々な人の力を借りて、生まれ変わったのだ。弱い「私」の皮が剥がれ、何事にも立ち向かおうとする「ぼく」になったのだ。
高三の夏。「ぼく」は袴姿で、選手達に「エール」を送っている。背後から、F先生やナリの声援が聞こえてくる。
産経新聞社主催
第38回オート・スカラシップ「高校生文化大賞」産経新聞社賞
[ ←back
] |



