
家族っていいなぁ
論文コンテストは「愛」がテーマ。部の顧問をしている私は、最近、文章指導の中に「家族を考える」をモチーフにすることを試みている。人と人との結びつきの原形「家族」をみつめることが、現代を生きる生徒たちにどうしても必要なのだという信念からだ。
しばらくして永美子が書き上げた論文には、ごく普通の思いや希望が語ら
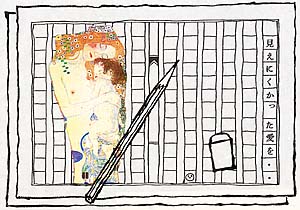 れていた。しかしその中で、ひとつの表現が私をとらえた。「ものを言わない父がこわかった。父の前で自分がうまく表現できない」。そんな文章だった。
れていた。しかしその中で、ひとつの表現が私をとらえた。「ものを言わない父がこわかった。父の前で自分がうまく表現できない」。そんな文章だった。「ひとはどこから来て、どこへ行くのか」は、私の好きな言葉だ。私は永美子に、もっと家族の成り立ちや両親の生きてきた時間を考えてごらん、と言い「自分はどこから来て、どこへ行くのか」を考えるよう促した。永美子の父親が数カ月前に亡くなっていたのを彼女の原稿で知った。その時、何かを表現したいと思い立った彼女の気持ちが分かるような気がした。
永美子は父親に、その生い立ちをたずね、彼が愛情不足の不遇な幼少期を送ったことを知り、こう書いている。「父は、生い立ちの中で自分に欠けていたものを、自分の人生の中で補っていったのではないか。人と人とのつながりとか、家族や他人に対しての愛情の持ち方とか」。そして不器用で、ぎこちない父の沈黙の意味を、ようやく理解する。病に倒れてから死までの二カ月間を彼女はつづっている。「私たちは居間ではなく、父の寝ている寝室で、できる限り父とともに過ごそうと話し合った」。そして毎日寝室で食事をした家族の日々を振り返り「楽しい一家団欒(だんらん)だった。どんな食べ物もおいしく、どんな会話も楽しくてならなかった。その時間は私の人生の中で一番価値あるものに思え、生きている実感がした」
永美子の論文は、文部大臣奨励賞を受賞し、ご褒美のアメリカ旅行をも体験した。永美子は「家族の歴史」を糸のように紡いで文章にした。論文の最後、父が死ぬ間際に「こんな家族を持てて幸せだった」と言うところで私は泣いた。その涙は悲しみのためではなく、人間っていいものだな、とあらためて人に対する希望のようなものを感じたからだ。永美子は父の死を通して「父の生き方」と「生きることの大切さ」を問い続けているのではないだろうか、今も。
2001年10月27日掲載 <3> |
| メニューへ戻る |
|---|