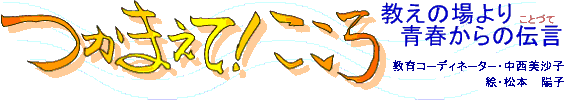
「教えられる」を忘れては
私たち教師は、「教えること」の日常を生きている。勉強だけでなく、心の在
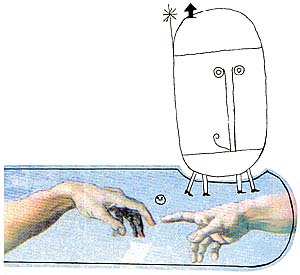 り方についても。しかし、この仕事には一歩間違えると、とんでもない落とし穴が潜んでいる。目下の人間を「教える」生活が、教師の在り方をひとつのパターンにはめ込んでしまうことだ。それは、「教えること」が、いつの間にか先生を、偉くて間違いのない人間のように錯覚させてしまうこと。教師という職業にとって、これは避けられないつまずきなのかもしれない。「教えること」で、どうしても自分の目線を上に置くようになる。そういうことに抵抗感がなくなる。その危険な意識は、知らぬ間に先生に巣くい始める。すると、いろんな形で送ってくる生徒の信号を読み取れなくなり、自分に反発する生徒を嫌ったり排除することに、痛みを感じなくなったりする。
り方についても。しかし、この仕事には一歩間違えると、とんでもない落とし穴が潜んでいる。目下の人間を「教える」生活が、教師の在り方をひとつのパターンにはめ込んでしまうことだ。それは、「教えること」が、いつの間にか先生を、偉くて間違いのない人間のように錯覚させてしまうこと。教師という職業にとって、これは避けられないつまずきなのかもしれない。「教えること」で、どうしても自分の目線を上に置くようになる。そういうことに抵抗感がなくなる。その危険な意識は、知らぬ間に先生に巣くい始める。すると、いろんな形で送ってくる生徒の信号を読み取れなくなり、自分に反発する生徒を嫌ったり排除することに、痛みを感じなくなったりする。ここ何十年間かの教育の現場は、小学校から高校まで、大学受験を最優先させてきた。それは社会のニーズでもあった。そのような教育が見失ったものは、「生きる力」や「やさしさ」。確かに学力も大切だ。好奇心や知識欲が生まれるのも「学ぶ」ところにあるから。しかし今の「学ぶ」は、記憶する技術が優先していて、学ぶことを支える「感動」がない。
「感動」がない教育の場では、より先生は生徒に対して尊大になりやすい。勉強だけが先生と生徒を結ぶ絆(きずな)になっているところでは、互いに思いやる心が芽生えにくい。そこは、より「教える」が「教えてやる」にすり代わりやすい場なのだ。
学校は、生徒と先生が「共に学ぶ」場でなくては、と思う。「教えること」と「教えられること」は、常に、同時に、ある。本当に、生徒から学ぶものはいくらでもある。特に「悪い生徒」とレッテルを張られた子供たちの近くにいると、その子供を育てた大人の生き方が、そのまま現れていると感じる。そしてそういう社会を作っている自分も、その一部であることに、打ちのめされたりする。
教えることのあやうさは、どこでも、だれからも「教えられる」ことを忘れたところに生まれるのだろう。
バス停の人込みを見る度、あの先輩先生の言葉が、警鐘のように鳴っているのが聞こえる。
2001年11月25日掲載 <5> |
| メニューへ戻る |
|---|