
万感の思い託し「蛍の光」
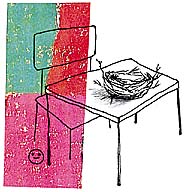 別れに対して「巣立ち」という言葉を、私たちは何げなく使う。三月。この季節になると私はいつも、その言葉の意味をかみしめる。
別れに対して「巣立ち」という言葉を、私たちは何げなく使う。三月。この季節になると私はいつも、その言葉の意味をかみしめる。鳥の親は、雛(ひな)鳥が飛べるようになるときっぱりと、別れを告げる。それが「巣立ち」だ。冷酷と思われるほど、その別れは厳しい。しかし雛鳥は「巣立ち」が始まるまでは、温かく保護されて育てられる。そこに私はいつも教えられ、考えさせられる。愛情をバックボーンに雛鳥が「巣立つ」ことができるとしたら、私は生徒たちの心に、「巣立ち」の力を与えられたのだろうか、と。
どの生徒にも公平で、慈しみのある心で接することができただろうか。間違いや感情で、生徒を知らぬうちに傷つけてしまったのではないか。『絶対自分は正しい』先生にならないよう、私は自分を戒めてきた。それは、先生だって矛盾を抱え、間違うこともある人間だということを知っているからだ。そのように生きていなければ、生徒たちの声を聞き分けることができないと思っているからだ。
三月一日。今年も生徒たちの「巣立ち」が行われる。卒業式。人生のひとつの段階を終えるお祝いの日だ。いつの時代にも、どこの国でも、新しい門出に人は祝福をした。花を贈ったり、物をプレゼントしたり。そして一番端的に心を託すことができるのが、歌う、ことだったのだろう。中国にも韓国にもヨーロッパにも、互いに歌をうたう、あるいは詩歌を詠む風習の跡が残っている。
「蛍の光」は、別れの古い歌だが、その歌詞は美しく、心にしみる。別れる者たちにとって、一番大切と思われるフレーズがあるからだ。『幸きくとばかり歌うなり』。これは「交互(かたみ)に思うちよろずの心の端をひとことに」(お互いに思う幾千幾万の気持ちをたったひとつの言葉で表すとしたら)に続くフレーズだ。万感の思いを託すに、その言葉以上の何があるだろう。「巣立ち」の後の厳しい現実を乗り越えるには、ただ『幸きくあれ』、つまり幸福であってほしい、という願いだけだ。そこには、私も元気でいるから、あなたも何があっても元気で生きていってほしいという思いが込められている。
互いに思いやる心を支えに、人は生きられる。そういう人間のきずなであってほしいと願いながら、私は今年も力いっぱい「蛍の光」を歌うだろう。幸きくあれ、幸きくあれ、と。
2002年2月23日掲載 <15> |
| メニューへ戻る |
|---|