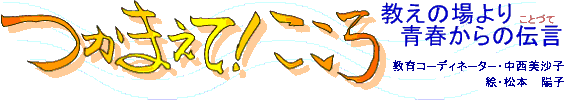
『いじめ』の底に大人の『不安』
教師をしていたころ、よく「いじめ」の相談を生徒や先生から受けた。その相談が近年とみに増え、「いじめ」の性格も変わってきている。以前の生徒同士のいざこざは、互いを説得し「ともに生きること」がどんなに大切かを説くと、「和解」するのがほとんどだった。「いざこざ」が、友としての深い絆
 (きずな)になることすらあった。しかしこの十年を境に、「いざこざ」は「いじめ」に変わり、「犯罪」に近い様相すら帯びてきている。暴力やお金の強要よりも酷(ひど)い精神的リンチを、多数で一人の生徒に加えることだ。「してはいけないこと」という感覚なしに、どこまでも執ように続くのが、怖い。そこに子どもたちの心の奥にひそんでいる、暗く青ざめたマグマのようなマイナスのエネルギーの強さを、感じるのだ。私は身の回りで起こる「いじめ」に対処しながら、いつも思うことがあった。「いじめ」はどこか私たちの営む「共同体」と似ていると。
(きずな)になることすらあった。しかしこの十年を境に、「いざこざ」は「いじめ」に変わり、「犯罪」に近い様相すら帯びてきている。暴力やお金の強要よりも酷(ひど)い精神的リンチを、多数で一人の生徒に加えることだ。「してはいけないこと」という感覚なしに、どこまでも執ように続くのが、怖い。そこに子どもたちの心の奥にひそんでいる、暗く青ざめたマグマのようなマイナスのエネルギーの強さを、感じるのだ。私は身の回りで起こる「いじめ」に対処しながら、いつも思うことがあった。「いじめ」はどこか私たちの営む「共同体」と似ていると。人の集まる場所。職場や住宅地、学校の父兄会や遊びの場でも、子どもたちが起こす「いじめ」に似た行動が見られる。新聞やテレビが伝える、共同体での大人の「いじめ」の深刻さが問題になっている。原因の底には、大人が抱え込んでいる「不安」が見て取れる。「学歴の差。出世。子どもの能力違い。財力。その人々の個性や能力の違い」。それらから生まれる妬(ねた)みや不安から「いじめ」が企てられる。自殺や、隣人間で起こる殺人事件も、そんなところに起因しているのではないか。いつから私たちの「共同体」はそんな心の歪みを友としたのだろうか。やりきれなさの半面、その生き方のつけが、子どもの「いじめ」につながっているのだと感じる。私たちが生き方を変えない限り「いじめ」は終わらないのだ。家庭という小さな共同体の中でも、「他人の悪口。家族の誰かを子どもの前でおとしめる」ことが行われているのではないか。「いじめ」をする子どもの言動から、そんな光景が見えてくることがしばしばあった。そんな環境の中では子どもは優しくなれないし、思いやる力は結べない。自信のなさと「不安」が、子どもたちの心に巣くうだけだ。大人たちが作った「不安」の影をもろに浴びながら、子どもたちは「いじめ」に走る。そう思えてならない。(この稿続く)
2002年8月31日掲載 <35> |
| メニューへ戻る |
|---|