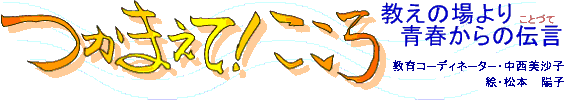
物拾う人の美しさ
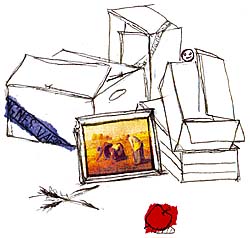 フランスの女流映画監督、アニエス・ヴァルダの「落穂拾い」という映画を見た。物を拾う人々を丹念に記録していく映画だった。カメラは捨てられた食べ物を、まるで生きているもののように写しとっていた。不思議なことに、捨てられたジャガ芋や林檎(りんご)がとても美しく感じられた。そして腰をかがめて拾う人々の動作も、どこか上品で神秘的ですらあった。「規格から外れた野菜。売れ残ったパン。箱の中で見捨てられた果物」。それを拾う人のショットが繰り返される。私は食べられる物を捨てる社会の理不尽さよりも、拾うことで生活を支えている人の、屈託のない表情に驚かされた。特にパリの朝の市場に打ち捨てられた食べ物を拾う青年に、目を奪われた。カメラに向かって、彼は野菜や果物の「固有名詞」を淡々と語る。「チコリ」とか「アンディーブ」とか。彼の物言いから、その食べ物はまるで自己主張するかのように輝いてくる。
フランスの女流映画監督、アニエス・ヴァルダの「落穂拾い」という映画を見た。物を拾う人々を丹念に記録していく映画だった。カメラは捨てられた食べ物を、まるで生きているもののように写しとっていた。不思議なことに、捨てられたジャガ芋や林檎(りんご)がとても美しく感じられた。そして腰をかがめて拾う人々の動作も、どこか上品で神秘的ですらあった。「規格から外れた野菜。売れ残ったパン。箱の中で見捨てられた果物」。それを拾う人のショットが繰り返される。私は食べられる物を捨てる社会の理不尽さよりも、拾うことで生活を支えている人の、屈託のない表情に驚かされた。特にパリの朝の市場に打ち捨てられた食べ物を拾う青年に、目を奪われた。カメラに向かって、彼は野菜や果物の「固有名詞」を淡々と語る。「チコリ」とか「アンディーブ」とか。彼の物言いから、その食べ物はまるで自己主張するかのように輝いてくる。私はふいに、忘れていた生徒たちの姿を思い出していた。色々な事情で学校に居られなかった生徒たちを。不遜(そん)な言い方をすれば、私は映画の中の青年のように、子どもたちの心や定まらない生き方を拾ったり、掬(すく)い上げるに十分なことができただろうか、と思った。「出来るだけのことはした」と自分では思っていても、そこに自己欺まんやヒロイズムはなかったか。映画は私に問い掛けているようだった。そのくらい彼の物言わぬ食べ物に対する態度は、優しく感じられたのだ。
「落ちこぼれ」と私たちは生徒にレッテルをはる。ためらいや、大した抵抗もなく。理屈を言うのではないが、「落ちこぼれ」るのは成熟した稲や麦そして果実なのだ。しかし私たちは何気なく、成熟していない子どもたちへの評価としてその言葉を使う。人を物に例えるのに少し抵抗があるが、「落ちこぼれ」の原因はどこにあるのか。それは、「落穂拾い」を丁寧に、そして根気強くする社会がないからではないか。私にはそう思える。
映画にも出てきたが、ミレーの有名な絵に「落穂拾い」がある。そして「種をまく人」と「麦を刈る人」をもミレーは描いている。生きる糧を得るための作業のすべてが、そこにある。教えの場にそっくり当てはまるような絵だ。しかし私たちの教育の場はいつの間にか「種をまいて刈り入れる人」だけが目立ち、「拾う人」の姿は消えつつある。ミレーの絵や映画「落穂拾い」は、拾う世界があってこそ平安で心が解放される世界があるのだと言っているように思えるのだ。
パリの市場で食べ物を手に入れた青年は、つまらない社会批判などしないで、アパートに戻って行く。そして夜になると、仕事に疲れた外国人にフランス語を教える。チョークを手にした姿に、そっくり「物拾う人」の美しさがあった。そしてその背は、「拾う人」はまた「拾われる人」でもあることを告げていた。
私たちは子どもたち一人ひとりに、輝く「固有名詞」として触れているだろうか。
2002年10月12日掲載 <39> |
| メニューへ戻る |
|---|