
『信じる』ことを求めて
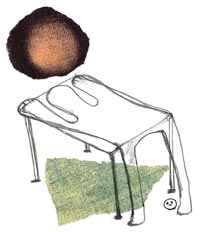 ない。自分が誤解されたと思った時、無視されたと感じた時、彼女は動物のような声を上げて教壇や机、廊下に体を伏せ、張り付くのだ。「ガラスで出来た爆弾」。それが彼女だった。見方を変えればわがままで、困った生徒の筆頭に、いつもいた。
ない。自分が誤解されたと思った時、無視されたと感じた時、彼女は動物のような声を上げて教壇や机、廊下に体を伏せ、張り付くのだ。「ガラスで出来た爆弾」。それが彼女だった。見方を変えればわがままで、困った生徒の筆頭に、いつもいた。私たちは少し変わった人の行動を見ると、その身振りや動作に眼を奪われて「なぜ」と考える事を忘れがちになる。とくに学校などの組織にいると、生徒を表面的に見る傾向になる。さらに、一人ひとりの問題にかかわっていられないという思いがふつうの感覚になってしまう。私にも、無意識のうちにそんな感覚があったのだろうか。彼女と接することで、それが怖いものだということを知らされた。
ある日、私は彼女のクラスの担任から助けを求められた。噂どおりだった。目の当たりに彼女が叫び声を上げながら机にしがみついている姿を見ると、その異常さだけに打ちのめされ、「なぜに?」という思いが起こらなかった。数人の先生が彼女を机から引き離そうとしていた。力を込めれば込めるほど、彼女は抵抗を強めた。私はとっさに彼女の上におおいかぶさり、その背を撫(な)でた。なぜそうしたのか、わからない。ゆっくり優しく撫でると、力んでいる体が穏やかになっていった。興奮が覚めると恥ずかしそうに彼女はほほ笑んだ。「怒りと穏やかさ」。その落差の中で、私はその生徒が「身を持って抵抗する」意味を、考えていた。
穏やかになりながら彼女は、「私はちゃんと約束を守ったのに。誰も信じてくれない」。そんな言葉をつぶやいていた。「信じてくれない」その出来事を、彼女は言葉少なに告げた。
『信じる』は『信じてもらう』ことによって成り立つ。今の時代ほどその思いが薄い時代はないだろう。私はその思いを彼女が表しているのだと感じていた。
子どもたちの行動は、こちらが受け入れる形で見つめさえすれば、『何らかのシグナル』になるだろう。私は彼女の変わった行動から、言葉ではない重みのある『大人への警告』を学んだ。彼女の必死の行動は闇に光る星のように誰にでも見える。しかし昼間の星は見えない。懸命にシグナルを送っても、見えにくい。『不信』の内に登校拒否になったり、引きこもりに逃れる生徒が、昼間の星のように私には思えてならない。
「机が好き」な少女は大人になった。卒業の時期になると毎年、スイートピーの花束が彼女から届く。その可憐(かれん)な花が、私には昼間の星の輝きのように見えるのだった。
2003年1月11日掲載 <48> |
| メニューへ戻る |
|---|