文章教室スコーレ
静岡県浜松市中区
元城町 219-16
TEL: 053-456-3770
FAX: 053-456-3795
|
 |
 |
 |
 |
 |
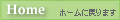 |
 | |

「家族」を拓く
鷲山拓見(高2)
「家族」を拓く
その日は、母の看病のために祖母が家に来てくれていた。習いたてのピアノを披露する弟や、勉強の悩みを吐露する兄。また、祖母の手料理を頬張りながら談笑する父。祖母はにこにこと笑いながら、ただその様子を眺めている。いつもそうだった。その日の夜、祖母は家に帰ると、既に床に就いていた祖父に向かって、僕たち家族の話をした。「あの子はピアノも上手だし、お手伝いもしてくれる本当に良い子だよ」と、小学五年生の孫の成長を心から喜んだ様子だった。
祖母が、突然、亡くなった。そこから僕が「家族」に抱いたイメージは、ジグソーパズルである。その断片であるピースを失うこととは何か、僕は考えた。
僕は日常の中で、家族を意識することはほとんどない。家族は当たり前のように存在し、互いに時間を共有し、それぞれの立場で生活している。家族を成り立たせているのは「寄り添う」ことと論を立てる人もいる。思想家の吉本隆明は『ハイ・エディプス論』の中で、「人が家族を作ろうとするのは『欠如』にある」と語っている。互いに足りないものを埋めようとする欲望が家族を形成するのではと。離婚はその欲望が過剰に起こるところに現れるとも論じている。
自分に足りないものを求め、寄り添うのが「家族」だとしたら、「家族」とは不安定な存在かも知れない。
日本の歴史を辿って考えてみると、江戸時代の家族制度は、封建制というシステムの中に織り込まれていたと言える。「家族制度」が家族のあり方を規制していたのだ。明治以降の家族も江戸期の倫理をもとに生きていた。その背後にあったのは、富国強兵や殖産興業などの政策であった。国を挙げた軍事力と産業振興に取り組んで行く為には、「大家族制」が必要だったのだ。その「家族」とは、作られた「家族」だった。
終戦と共に、国家の強制力から離れた家族は、「家族」の在り方を、自ら考えなくてはならなくなった。だが「民主主義」という「自由」を、「家族」という形にすることを、戦後の日本人は、未だ見付けていないのではないか。
映画から見た家族
「映画は時代を端的に映し取るもの」と聞いたことがある。その時代の風俗や人々が使う言葉の変化、映像の背後にある風景などが描かれているからだろう。そこで、僕の祖父母が若い頃に公開された『東京物語』、両親の年代の『男はつらいよ 寅次郎恋愛塾』、そして僕の時代の映画である『万引き家族』を取り上げ、家族について考えて見たい。
『東京物語』
1953年、小津安二郎監督によってつくられたモノクロ映画、『東京物語』。尾道に住む老夫婦が、子供たちの住んでいる東京まで会いに行く。この映画を見たとき、旧約聖書「創世記」のアダムとイブの話とが重なった。
「彼女はみごもり、カインを産んで言った、『私は主によってひとりの人を得た』。彼女はまた、その弟アベルを産んだ」。これは、イブの子供が産まれ、人類にとって初めて、「家族」というものが創られる場面である。カインは後に些細な出来事から、弟のアベルを妬み殺してしまう。いったい僕は、この話と『東京物語』のどこに通じるものを感じたのか。
様々な物事の普遍的原型を表すものが神話である。アダムとイブの話も、家族形態及び親子関係においての原型になっていると考える。アダムとイブの子供であるカインを神話に置いたのは、「弟殺し」という「歪んだ家族」が、家族の原型だと考えたからだろう。言い換えれば、危うい存在こそが「家族」なのだろう。『東京物語』からも、そんな家族の危うさと、その崩壊の予兆が見てとれる。
『東京物語』は、僕にとって一つの衝撃だった。不思議なシーンがあった。突然のように、干された家族の洗濯物が、風になびいているところだ。モノクロの映画だが、色彩を感じさせる場面でもある。それを僕は家族の象徴のように感じた。
『東京物語』の中で、娘が老夫婦に対して熱海への温泉旅行をプレゼントするシーンがある。一見すると親孝行で心優しい娘のようにも思えるが、そのシーンからは、親に対する疎ましさや両者の文化観の違いが感じられた。老夫婦が東京に来たことに対して、それを心から喜んでいる者はいない。子供たちは地方都市である尾道から大都会東京に出てきて、自立し、家族を持ち、各々の生き方を形成している。老夫婦もそれを「こんなものか」と許容している。僕はこの老夫婦に、アダムとイブの年老いた姿を見た。
老いた母は、東京から尾道に帰ってすぐに体調を崩し、そのまま亡くなってしまう。「暇乞い」と呼ばれる言葉がある。それは、死に際した人間が自分の家族や友人に会いに行き、別れを告げることだ。それはその人にとって、今までの人生の肯定であり、死ぬ前に自分たちが成したことを、もう一度見つめ直すことでもある。『東京物語』には、家族の生き方への極めて覚めた目がある。
『男はつらいよ 寅次郎恋愛塾』
山田洋次監督による『男はつらいよ』は、1960年代半ばに始まった人気シリーズである。『男はつらいよ』は毎回、放浪者である主人公の寅さんが、突然故郷に帰って来ては、その度に家族内を波立たせるような騒動を起こすというストーリーである。その中で、日本がバブル景気に沸いていた1985年に制作された『男はつらいよ 寅次郎恋愛塾』という作品に焦点を当てて考えていこうと思う。
寅さんの実家の家業は、下町の団子屋である。帝釈天という寺の門前町で団子屋を営んでいる。この映画から感じるのは、ユートピアのような世界である。山田監督は、人間の持っている負の感覚を意図的に避けているようにも見える。それは日々の生活で生まれる人の「悩み」や「諍い」などを、心をこめて描いているところがあるからだ。人間の営みが、「団子」や「食卓」、「人と人との声の掛け合い」を通して、香ばしい煮物のように漂ってくる世界が、その映画にはある。ある意味で現実離れした世界が『男はつらいよ』にはあるのだ。このユートピア映画は山田洋次が描いた、「家族」へのオマージュではないか。
寅さんという人物がこの映画の核であるが、家族の中心にはいない。不意にやってきて問題を起こし去ってゆく。他の『男はつらいよ』も同じパターンで描かれている。喜劇映画だから、「笑い」が映画のモチーフであるが、寅さんとは、「家族」にとってどのような「人間」なのだろうか。
寅さんは、すぐに女性を好きになって、その後失恋するが、その騒動に対して家族は「迷惑」と感じるだけでなく「気を揉む」という両義的な気持ちを持つ。ときに言動が乱暴であるが、寅さんは優しさもある人物なのだ。
国文学者の折口信夫と、民俗学者の柳田國男との「日本人の神と霊魂の観念そのほか」についての対談で、寅さんのような「ヒト」が語られていた。それは、「マレビト」という神的な存在についての話であった。折口は「マレビト」を、神となって旅するものたちではないかと論じる。
折口は「何故日本人は旅をしたか、あんな障碍の多い時代の道を歩いて、旅をどうして続けていったかというようなところから、これはどうしても神の教えを伝播するもの、神々になって歩くものでなければ旅は出来ない、というようなところからはじまっているのだと思います」と言っている。それを受けて柳田は、「常世神が一番はじめですが、仏教以前の外教宣伝者のことが幸いに同時代の文献に出ています。常世神は、あの時はたしか駿河国でしたね。あの記録以外にも、旅人が信仰を以って入って行ったというようなことがあるのでしょうか」と折口に問うている。
僕は「マレビト」と「常世神」は同じもので、彼らは映画に出てくる寅さんと重なると思う。柳田は「マレビト」が、駿河国にやって来て、その村で少し乱暴な行為に及んだことを記している。村人はその行為を拒否するのではなく、大きく受け入れていたことが柳田の話から想像できる。僕は「マレビト」という存在の意味は、家族や共同体という内なるものとの関係にあると考える。それは家族や共同体の中に必然のように起こる「馴れ」と「淀み」への恐れではないかと。
『万引き家族』
2018年に公開された是枝裕和監督による『万引き家族』。孤立した人々が疑似家族を作っている姿を描いたのが、『万引き家族』だ。教養もお金も能力もない男や、親に捨てられた子、親から虐待を受け孤独に生きてきた少女などが、共に寄り添い、互いを補い合う。誰かを支えることで自分も支えられるという意識で、血縁関係のない者が結びつく。家族の基本である「互いに寄り添う」ということが、今の日本では希薄になっている、というのが映画の印象だ。
この映画を見終わったとき、僕の心にはやるせない気持ちだけが残った。帰り道、一緒に映画を見に行った父にふと、質問を投げかけた。なぜ医師になろうと思ったのか、と。僕が唐突に父に訊いたのは、「万引き家族」と「自分の家族」とを重ねたからだ。職の選択は、「家族を創ること」と大きな関係がある。僕は父がどうやって家族を創ってきたのか、そのルーツを、この映画を通して知りたくなったのだと思う。
映画の中で、母親から虐待を受けている少女が出てくる。その家庭では、母親も夫からDVを受けるなど、家族間での大きな歪みを感じる。少女はその後、はみ出し者が集まった「万引き家族」に拾われて、その中で家族の温かみや無償の愛を感じていくのだ。
厚生労働省の児童虐待相談の対応件数は、平成11年度に11631件だったのに対して、平成28年度にはその十倍以上の122578件もの相談があった。また、平成11年度から平成28年度にかけて、その値は常に増加傾向にあった。この統計からも読み取れるように、現代日本は家族間や親子間に何らかの問題があり、それは年ごとに増加傾向にある。
映画の中でとても印象的なシーンがあった。家族の「父役」の男が事情聴取を受けているときに、「万引きぐらいしか子供に教えてやれることがなかった」と呟くシーンだ。万引きは犯罪であるが、親子関係を繋ぐものとして、どうしても必要だと監督は考えたのではないか。親は子に、何かを「教える」ことをする。生きる術や、家族の歴史など、子は親を見てそれを学ぶ。それは、子と親、また家族が気持ちを繋ぐために重要なことだ。
この映画から僕が感じたものは、現代家族の劣化だ。特に親と子供との関係が希薄になっているのではと。
その要因の一つは「過剰な経済」ではないだろうか。高度成長時代の日本経済は、大量消費によって成り立っていた。消費が動くことは、豊かさであり、様々な商品はその象徴でもあり、衣食住の安定と共に精神を柔らかにしていたのだ。だが大量消費の悪しき形のバブル時代が起こり、家族のあり方を変容させていったのではないか。
良い大学、良い企業に向かって親は、子供に「学ぶ」ことを勧める。その思いの根にあるものは、「過剰な経済」ではないだろうか。「互いに寄り添う」ことよりも、それが優先されていると考える。
『万引き家族』の家族は「疑似家族」であるが、是枝監督は、今の家族の在り方を訴えているのではないかと、僕は映画から受け取った。
三本の映画から
時代を追って三本の映画を分析してきたが、現代に近づくにつれて、「家族」というものが時代によって変化し、悪しき方向に向かっているのではないかという印象を受けた。
終戦に至るまで、国の枠組みの中にパーツとして存在していた家族。『東京物語』では、檻としての「大家族制」から離れた「迷える家族」が描かれていたと僕は思った。そして、家族の「馴れ合い」の中でいつの間にか「淀み」が生まれ、その淀みを撹拌する人物として、山田洋次は寅さんを描いたと思った。家族の崩壊と、今の時代の家族に対する価値観に疑問を投げかけたのが『万引き家族』ではないか。三本の映画を見て僕は、自分なりの「家族」とは何かを模索してきた。
その中で特に『万引き家族』から受けた思いは、現代の家族には未来はないという息苦しいものだった。だが目を開いて見れば、あの「疑似家族」のように「互いが寄り添う」新たな家族が、曖昧ながら見えてくるのだった。現代に蔓延する多くの家族問題を見ていると、日本人は何か大きな「忘れ物」をしてきたように思える。その「忘れ物」とは何かを辿ってみたい。
家族を創ってみる
『大家さんと僕』。この漫画は、漫画家であり漫才芸人でもある矢部太郎の作品だ。メディアでも多く取り上げられているその漫画は、41歳の矢部自身と87歳の大家さんとの間に生じる不思議な関係を描いている。二人の間には、「互いに生かされている」という家族の原型を感じさせるものがある。その漫画の中で、芸人の誕生日に大家さんがケーキをプレゼントするシーンがある。ケーキといっても、おはぎに仏壇用のロウソクを立てただけの質素なものだ。おそらく大家さんは、毎日仏壇で手を合わせ、先祖を想って生きているのだろう。独り身の大家さんにとって、過去との繋がりが唯一の「心の拠り所」であるのかもしれない。
先祖とは何か、僕はこの漫画をきっかけに考えてみた。大家さんが「心の拠り所」にしたのは過去の人たちへの思いの総体ではないか。両親やそれに繋がる人々や、今は見えないが過去に確かにいた人たちへの思いが、おはぎのケーキのシーンにはあるのだ。先祖は過去の人たちのことではなく、今を生きる人たちへのメッセージではないかと。それは「生かされている」という思いと同じだ。その思いがあって「未来の家族」が見えてくる。
メキシコには「死者の日」という大切な祭りがある。その日の食卓には、家族だけではない「不在の人」のための食べ物を置くというのだ。この祭りも先祖への思いを形にしたものであり、未来の人たちへと結ぶものではないか。
だが今の時代は、「生かされている」という意識が薄く、目の前にあるものだけに囚われる傾向がある。言葉を換えれば、人と人との関係や家族にある「文化」が希薄になっているのだ。矢部太郎も大家さんとの関わりの中で、その意識や文化を徐々に受け継いでいったと、僕は本を読みながら実感した。
また『大家さんと僕』の魅力は、血縁や利害を仲立ちとしない無償の関係が描かれているところだ。誰かを支えることで自分が支えられる。誰かを愛することで自分が愛情を享受する。そんな二人の関係は、「未来の家族」を示唆しているのではないか。
それを感じさせる印象的な場面がある。大家さんが血圧を測りながら、「死ぬまでに一度、チランに行きたい」と呟く一コマだ。「チラン」という大家さんの言葉に、矢部太郎はその意味を掴めずにいる。大家さんは矢部を誘って旅に出る。矢部は「チラン」がどんなところか理解していないが、咄嗟に「一緒に行きたい」と言うのだ。年老いた大家さんが「行きたい」と言った思いの奥にあるものに彼が反応したのだろう。大家さんと矢部が行った場所は「知覧」だった。その場所は第二次大戦時に特攻基地だった。この漫画の「知覧」での話は、知覧特攻隊資料館を見たところで終わっている。大家さんが年老いた体に鞭を打ち、命をかけて鹿児島の知覧まで行ったのは、矢部さんに「伝えたいこと」があったからではないか。想いを「伝える」ことは、過去と今を貫き、そして未来へと繋げるものではないか。僕が『大家さんと僕』から受けたものは、「未来の家族」の在り方の手本だった。
矢部太郎と大家さんの関係は、「心の拠り所」と「伝えること」とで成り立っていた。僕は、そこに家族の原像を見る。
「未来の家族」
新聞やテレビニュースで、「家族を失った人たち」や「家族から孤立」している人々の問題をよく目にする。「孤独死」や「児童虐待」、「離婚率の多さ」などが典型な例である。そんなニュースを目にする度に、「家族」が溶けかかっていると感じるのだ。
そのような状況を、少しでも変えることはできないか。血縁の家族だけではない、他者との関係に繋がる家族の在り方が重要だと思うのだ。
現代では、「share」という言葉をよく耳にする。この言葉は、場所や空間を共有することを示している。「share」という言葉に、僕は抵抗がある。機械的に時間や場所を分け合うというようなイメージがあるからだ。そこで生きている人の息遣いや思いを共有しながら、なお且つ息苦しくならないような人々の集まりができたら、と想像してみる。それを僕は「創造する家族」と呼びたい。
老若男女が集まる場。深い経験と、新鮮なアイデアが共に存在する場。そんな空間は、豊かに「家族」を彩る。枠を超えた、他者との関係での家族は、孤独な者に「支え合う」ことを教え、何かを「伝える」。そんな家族の核になるものは「文化」だと考える。それは音楽を奏でたり、共同で絵を描いたりするような「文化的共有」であっても良い。現代の問題点や可能性を議論する場所であっても良い。互いに調理し食を楽しむことも良い。それぞれが持っている資質や感性の違いを生かしながら、自由な空間を模索することなども「創造する家族」なのではないか。その考えに留まるのではなく、何時も更新する意識を持つことも重要だ。
そんな「意識の更新」を果たすものとして、僕の家では「家族会議」なるものが開かれる。開催は不定期だ。議題は、長期休暇での旅行の行先についてや、ちょっとした家庭内での意見交換である。先日行われた家族会議では、「家計のピンチにどのような対策がとれるか」。普段部屋にこもって勉強している兄も、家事に忙しい母も、家族全員がリビングに集まり、各々の考えをプレゼンした。そうして互いの考えを批評し合い、一つの結論とこれからの実践目標を導くのだ。この「家族会議」は、会議後の僕たち家族に一体感を与えてくれる。人はそれぞれ個性があり、長所も短所も持ち合わせている。家族内で議論することによって、互いの個性を認め合ったり、自分の弱点に気が付いたりすることができる。この「家族会議」は、我が家独特の「文化的共有」の場である。
僕の家の「家族会議」は、極めて個人的なものだが、公共の空間として創り上げることが、出来るのではないか。そのための空間作りには、建築家やデザイナー、そして社会学や思想家などの専門家も必要になるだろう。
今、述べたことの多くは、「家族の形」の模索だが、本当に重要なのは、「心を結ぶ」という目に見えないものへの思いだ。『大家さんと僕』に出てくる仏壇、その先へと続く先祖への思い。『男はつらいよ』の寅さんから考えた「マレビト」など、抽象的であるが、「神的なもの」とか「超越的なもの」への恐れを土台にして家族を考えることも重要だろう。
僕の父は、不思議なことを言うときがある。「今、『未来』を覗いているような気持ちになった」と。以前から父は、家族団らんの場において、たまにこの言葉を発していた。何を訳の分からないことを言っているのだろうと今まで聞き流し続けてきたが、先日、この言葉の意味について初めて父に尋ねてみた。すると父はこう答えた。「自分が子供の頃、親や祖父母、近所のおじさんなどから受けた愛情に、今になって気が付いたということ」と。父が幼いとき受けたアドバイスや、大人から送られた言葉の意味を、実体験を通して理解し、今、同じように僕たちにアドバイスをしているのだ。それは、父自身が経験の中で得たエッセンスとなり、より深みを増したものとして進化する。「伝承」という「文化」は、家族の大きな要素であり、それは見えない先祖との対話でもある。そのような意識を持ち続けることが、「未来の家族」であり、「創造する家族」となってゆくのではないか。
慶應義塾大学 主催
第43回
「小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト」
小泉信三賞 次席作品
|
[ ←back ] |



