文章教室スコーレ
静岡県浜松市中区
元城町 219-16
TEL: 053-456-3770
FAX: 053-456-3795
|
 |
 |
 |
 |
 |
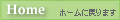 |
 | |

言葉は、時を超えて袴田優里子(高3) 「時を逸しない」。そんな思いや生き方があります。この夏、私は『福沢諭吉の手紙』を読んでそんな実感を手にしました。『福沢諭吉の手紙』は、一つの個性が歴史を作る、その現場にいるような気分を読む人に与えます。手紙という書かれたものは、どこか無防備です。心の平穏さや激しい感情、思いやりや批判などが、あまり抑制されずにあるからでしょうか。だからこそ、福沢の時代に敏感な姿勢は、手紙の中では何より鮮明に表れています。私は彼の手紙を読むことで、「時を逸しない」という姿勢が、人が生きてゆくうえで重要な意味を持つのだと感じました。彼の手紙からは、生な人間の息遣いが立ち上がってくるのです。これは手紙が持つ形式のため、とばかりは言えません。著作である『福翁自伝』には、自分自身を客観的に見る視点があります。しかし手紙には、客観性よりもある種の情動と切迫感が溢れています。そのエネルギーは、「時を逸しない」ことに意識を傾けた福沢の発する体温のように私には感じられます。福沢の手紙に、私は日付としてではない「生きた時」のようなものを感じます。特に「その時を逸しない」と「生きた時」が強く手紙の文面に表れるのは、大きく時代が変わろうとする時です。
慶応四年、山口良蔵宛の手紙に、「天下は太平ならざるも、生の一身は太平無事なり。かねて愚論申し上げ候通り、人に知識なければもとより国を治ること能わず。甚だしきに至りては国を乱したるにも規則なし。皆無知文盲の致す所なり。今人の知識を育せんとするには、学校を設けて人を教うるに若くものなし」という文面があります。ここでは学校設立への意志と希望が綴られています。
慶応四年は徳川幕府が倒れた年でもあります。「天下太平ならざるも、生の一身は太平無事なり」と福沢は心境を語りながら、天下の混乱の先にある理想を見ています。それが「生の一身は太平無事なり」と言わせたのでしょうか。幕末の混乱を横目で見ながら、学校設立の意義を、痛切に書き留めています。
明治維新と言われる国家体制の変革期に、彼は動乱に身を挺するより学問の在り方を考え、実行することを選びました。国家の体制が変わったとしても、世界を見る目や国家観、そして経済などを考える人材がなければ国は衰退する、と思ったのでしょう。
また、同じ年の山口良蔵宛の手紙には、「徳川家へ奉公いたし、計らずも今日の形勢に相成り、最早武家奉公も沢山にござ候。この後は双刀を投棄し読書渡世の一小民と相成り候つもり、さようご承知下さるべく候」とあります。多くの武士が権力闘争に明け暮れしている時に、福沢は自分の生きる形を「学問」に置いています。ヨーロッパやアメリカを巡って、日本に何が足りないかを福沢は的確に判断したのでしょう。「近代的な学問の普及」によって国を支える。政治や権力争いに関わっていては、彼の思いは果たせなかったでしょう。
慶応義塾の慶応は「その時を逸しない」象徴のようだと私には思えるのです。
明治十四年、井上馨・伊藤博文宛の長文の手紙。国会開設と民権に対する福沢の思いが端的に表れています。機微に聡い福沢の本領が、そこにもあります。また、「駄民権」ではない民権啓発のための新聞発行にこだわる福沢の姿勢も見えます。
「政府は国会を開くの意なりと。老生はこれを聞て実は驚 したるほどの事にて、先ずもってその英断美挙を賛成し、次第にその趣意を叩けば、君の言に云く。国会は断然開かざるべからず」。
明治十四年には政府内に政変が起こり、国会の基礎を固める、と福沢が考えていた政府機関紙『公布日誌』が立ち消えになりました。『公布日誌』は政府の刊行ではありますが、新聞の発行は国家国民にとって必要なもの、と福沢は認識していました。その編集を任されていたのが、突然中止になったのです。
この長い手紙には、怒りに近い感情が感じられます。「たとえば今の政府を病者と視做して、新聞発兌もってこれに応援するは、あたかも芥子泥発砲膏をもって一時の病勢を誘導して、軽快を覚えしむるものに異ならず」や「今の政府の内情を見よ。事を企て事を行う者は我輩三名にして、麑島参議のごときは傍観者に異ならず。ただの傍観者なればまた可なりといえども、自家の利害に関することに至りては、すなわち踏み止まりて屹然動かず。その勢力決して軽小ならず、もって施政の遅滞を致す、枚挙に遑あらず」などの文面には、理想を権力争いや面子などで貶められた者の怒りが、充満しています。
「時を逸しない」。「時を逸すること」で理想が先送りになったりすることが、福沢には耐え難いものとしてあったのでしょう。「時を逸しない」ことは福沢の理念や理想、そして生き方の核になっている、と手紙が私たちに示唆するのです。福沢は時代と共にありました。時代をつくった、と言っても過言ではないでしょう。福沢の手紙は、何を為すにしても「時を逸しない」意志や行動が必要だ、と私が生きている時代に語りかけているようです。
では、私が生きる時はどうでしょうか。二〇〇四年の現時点での世界と日本は、混乱の中にある、と言っても良いでしょう。アメリカの一国主義が世界にもたらした災いの全てを「イラク戦争」が表しています。パレスチナとイスラエルの問題さえ解決できない時に、アメリカは、新たな混乱の火種を置いたのです。ノーム・チョムスキーが『メディア・コントロール』の中で「イラクにアメリカが侵攻すれば、テロは世界に広がるだろう」と言ったように、今世界はテロの恐怖の金縛りになっています。自由が、テロの見えない影に怯えているのです。アメリカは大国のプライドを9・11テロで傷つけられました。その怒りを圧倒的な武力でアフガンに向けました。そしてその戦争の成果の余勢を、そのままイラクに向けました。アメリカはなぜテロ攻撃を受けたのか知っているはずです。しかしテロの原因を認識して行動する知的作業よりも、戦争という悲劇的パフォーマンスを選びました。「正義と民主主義」が「虚無と憎しみ」を生産するのを、ビジュアルなスペクタクルとして世界に提出したのです。私たちはその光景を何気なく消費しています。そして私たちの怒りややりきれなさは、形あるものに結実することなく、無関心という大きな虚無の中に取り込まれてゆきます。
アメリカは9・11を契機に戦争に進みました。そこには「時を逸しない」アメリカの意志があったのでしょう。しかし冷静な対応があれば、9・11は世界が変わるチャンスであったかもしれません。私は、アメリカは「時を逸した」のだと思います。
グラウンドゼロから始まった戦争は、世界に多くのグラウンドゼロを再現してみせるでしょう。
第二次世界大戦以後、アメリカの経済と軍事力の恩恵を受けて生きてきた日本も「イラク戦争」を肯定しました。北朝鮮や中国との関係、また対米貿易の重要さから、アメリカに迎合することが「時を逸しない」こと、と日本は認識したのでしょうか。しかしその行動には、独立国としての理想が見えません。日本はアメリカの主張をなぞるだけで、自国の展望や意見がなさすぎます。
文久二年、島津祐太郎宛の手紙に、「先ず当今の急務は富国強兵にござ候。富国強兵の本は人物を養育すること専務に存じ候」とあります。
明治は近代化を「富国強兵」に置きました。当時、世界の中でひとり立ちしてゆくためには、「富国強兵」である必要があったからでしょう。しかしその概念は、ナショナリズムや国家主義に傾いてゆく可能性を多く含むものでした。福沢も、「富国強兵」を説いています。しかし彼の言葉からは、ナショナリズムや国家主義といったものは感じられません。それは彼が、個人の尊厳や自由といったものを先ず優先する、そんな意味での「富国強兵」として、その言葉を捉えていたからではないでしょうか。
「一身独立」。この言葉は福沢の語彙の中で、一番重要な言葉でもあります。国を成り立たせる国民の意識と行動を支える思想です。手紙の中にも「一身独立」は書かれています。「一身独立して一家独立、一家独立一国独立天下独立と」。その一身を独立させるのは、知識を開くことだと福沢は説いています。個々人がその時代を認識し、行動すること。そんな理想が、今の日本には根付いていません。
理想のない現実主義は、過酷な現実を乗り越えることができません。理想という骨組みがあってはじめて、そこにある現実を意味のあるものにしてゆける、と私は思います。
福沢は明治に亡くなりました。彼は昭和という時代の戦争を予想できたでしょうか。福沢はなぜ『戦争論』を書かなかったのかと、この論文を書きながら私は思いました。文明国であった西洋諸国はまた、戦争を辺りにまき散らす国々でもあったのですから。
諭吉と漱石
福沢の手紙を読むと、不思議な感じを受けます。その違和感のようなものはどこから来るのでしょうか。私は、それは手紙の中にある漢語と英単語(カタカナ表記)、ひらがなの混ざった文体にあるのだと思います。現在の私たちの書く文章は、横文字や外来語を抵抗なく使います。しかし漢文的な表現は失われています。
福沢が英文読み下しを頻繁に使うのは、慶応二年から明治六、七年の頃です。「大君のモナルキ」のように後年有名になる言葉をはじめ、マインド、エレメント、ナショナリチ、モメント、ネーション、デスチニー、コミニスム、コモンセンスなどの英単語が、翻訳されずにそのまま使われています。
ナショナリチやネーションなどに含まれる意味は、現代でも、解決できていない重要な問題としてあります。福沢は多くの西洋思想を学びました。日本語に置き換えられない語彙を、そのままカタカナ表記で使っています。特に、塾生にあてた手紙にはカタカナ文字が多いようです。英語の語彙を共有できる者たちには、強いて英単語を使ったのでしょう。
言葉は、文化や歴史を端的に反映するものです。言葉が人間の考えを支配する、と言っても過言ではないでしょう。江戸時代は朱子学を国家の礎にしていました。俗に仁義礼智信と言われる儒教が、考えの元となっていました。江戸時代の封建システムを支えていたのが、儒教なのです。
武士階級は四書五経を理解することに努めました。それらの書物は漢語で表記されていました。それは、漢語で物事を考えた、ということでしょう。三百年有余にわたる漢語文化は、日本人の思考回路を決定づけていたのでしょう。「門閥制度は親の敵」と旧習を批判した福沢でさえ、その思考回路の網の目から逃れることは困難だったろうと思います。しかし福沢の手紙には、その漢語的思考と西洋的な語彙が同居し、互いを排除するのでなく、新たな思想を模索するような感じがあります。
彼の手紙には、西洋の語彙が持つ意味を日本語に置き換えられないもどかしさがあります。大阪の緒方塾でオランダ語を学び、西洋の合理主義に触れた経験のある福沢であれば余計に、日本語に置き換えられない言葉に日本の後進性を感じたでしょう。
しかし福沢の手紙には、日本の後進性を敗北としてみる見解はありません。それよりも、日本に欠けたものへの視線が強くあり、変革を急ぐ心の在り様が書かれています。
「死を守って」「天下武を知って文を修る」「恥死」などの旧習としての儒教的文体と、先進的思考を表す西洋の語彙が同居する福沢の手紙は、矛盾を孕みながら、決して儒教的な思考に囚われないものとしてあります。福沢の性格や気質にも関係するのでしょうが、それは彼の持つ合理的で柔軟な精神の表れのように、私には思われます。また、「ママヨ浮世は三分五厘、間違えたらば一人の不調法」などの、言葉遊びのような七五調のくだけた言葉遣いがあります。そこにも、彼の心の幅の広さのようなものが感じられます。
福沢が古い思考方法(無意識としての)で、新しい思想を語ることを挫折することなくできたのは、彼の強い「欠如感」だったように思えます。国家体制や個人の在り方を考える時、近代化が遂行されているアメリカやヨーロッパに日本の伝統や文化で対抗しなかったところに、福沢の希有な個性が生かされたのでしょう。こちら側の価値観に拘泥するのではなく、今何が必要か、という「欠如感」でものを考え、真っさらな精神で西洋と取り組んだ人間は、福沢をおいてないでしょう。
福沢は文芸や芸術にはあまり興味がなかったのか、手紙には、芝居見物の話題程度にしか芸術の話は出てきません。実学を通して具体的に変革することを目指した福沢と、目に見えない心の問題に取り組んだ夏目漱石を比較してみることは、福沢をより立体的に見せます。福沢が光であったなら、漱石は影のように、その両者があってはじめて明治という時代が掴めるのではないでしょうか。
漱石は福沢よりやや若い世代です。しかし、漢語文化の影響を受けながら西洋という異文化を体験したことは共通しています。彼は明治三十三年にイギリスに留学しました。
その頃の覚え書(岩波の漱石全集では断片)には、漱石の持つ価値観と、西洋の価値観との違いが書かれています。差異というより齟齬、と言ったほうが適切なものがあります。
○西洋人 感情を支配できない。
日本人 できる。
○西洋人 自慢をはばからない。
日本人 謙遜。
○西洋人 小説でも実をたっとび、理想の人間を描かぬ。
日本人 空漠としているかわりに理想の人間を描く。
○西洋人 神という大理想がある。
日本人 馬琴『南総里見八犬伝』の仁義礼智信という倫理を持つ。(抜粋)
漱石は漢語的教養をもって英文学に臨みました。留学して、自国の文化や価値観が、自分の中で崩壊するような感覚を味わったのでしょう。先に引用した文章からも、冷静な判断よりも、西洋の文化に対する嫌悪と挫折感のようなものを感じます。イギリスは漱石の生き方や考え方を否定するようにあったのでしょう。漱石の気質も作用したでしょうが、彼は精神まで病んでしまいます。それほどに漱石にとって西洋は手強い相手でした。
漱石が持っていた漢語的精神世界は、人と自然との融和を意味しています。しかし、十九世紀の西洋はまず人を、個人を優先しました。そこには合理的な意識を持った個人主義があったのです。そのような考え方を持った西洋は、世界の先進国でもありました。
後進国としての日本、また、自分が信じて足りる日本の伝統的文化観は、留学によって漱石に凄まじい「軋轢」を生みました。
漱石の偉いところは、その価値観の「軋轢」の中で、旧習としての日本文化に逃げ込まなかったところです。西洋がつくり上げた個人主義的人間の在り方と、日本文化の持つ価値観との衝突を、自分の作品の中で見つめました。『道草』の自伝的作品では、主人公がもつエゴに近い個人主義と、旧習としての人情がぶつかり合う場面が多くあります。そこに派生する自虐的嫌悪感も冷徹に漱石は見ています。漱石の多くの作品が、西洋との出会いの衝撃の痕跡を含んでいます。
「??夫だから善人は必ず負ける。君子には必ず負ける。徳義心のある者は必ず負ける。清廉の士は必ず負ける。醜を忌み悪を避ける者は必ず負ける。礼儀作法、人倫五常を重んずる者は必ず負ける。勝と勝たぬとは善悪、邪正、当否の問題ではない??powerである??willである。」(『断片』より)
西洋と出会った漱石の痛々しい焦燥感が右記の文章にはあります。しかし彼は、その「軋轢」を文学の中に持ち込み、近代人としての日本人を描きました。漱石は日本の近代化から派生する人間の苦悩を、どの作家よりも的確に描きました。その人間の在り方は私たち現代を生きる者にも多くの示唆を与えます。
現在の日本では、世界のグローバル化や異文化理解などの問題があらゆるところで喧しく語られています。世界の擬似文化が多量に交差して、止まることなく、時間の中に消えては生まれています。
ĄTの進歩と際限のない消費が代表する、高度資本主義の世界に私たちは生きています。マスメディアが人の欲望を生産し、人は自分の欲望を自己のものとすることが難しくなっています。もしかして福沢の文明論や漱石の文学が持つ国家観や人間観、そして個人や民主主義も、単なる情報として私たちは扱っているのかもしれません。いろいろな情報は人の表象にしかとどまれず、人の核心にはほとんど入ってきません。私たちは、自国の文化や価値観をまるで異文化のように見ます。それは、何かを相対化し客観的に見るコアが、私たちにないからかもしれません。
福沢は、「欠如感」をもって明治という時代を生き、様々な試みをしました。学校、経済、憲法や民主主義、女性の生き方。それらを考えるため、西洋の文明を取り入れるところから始めました。漱石は西洋との「軋轢」から、日本の近代や人間を見つめました。漱石は、福沢にはない文芸という形で時代を見つめたのです。そこから発生する様々な問題が、二人の残した言葉を辿ることで理解できます。福沢の語った文明や個人主義、そこに生まれる国家。また、漱石が苦しみの中で捉えようとした自国の文化と西洋の文化との折り合いなど。福沢の手紙と漱石のメモを読むと、内なる言葉と外なる言葉との格闘が見えます。その戦いは、日本語の持つ力と足りないところを認識することで成り立っているのです。
今、高度消費社会は進歩し、物質的に幸福感を感じる場面はあらゆるところにあります。そのような社会は、言葉をも消費の対象にし、また武器として扱います。笑い、悲しみ、怒り、優しさなどの人間の感情さえも、マスメディアの中で操作されつつあります。自己を生きるのではなく、多くの他人を生きるようなスタイルが定着し始めています。まるで演劇の中の登場人物のように。「言霊」という語彙があります。言葉が持つ力を魂に例えた言葉のように思えます。現代は消費経済を優先させるあまり、その「言霊」は殺されつつあると思います。
高度消費社会は、自己が自らの意思で語る言葉を裁断するようにある、と私は思います。ケータイやインターネットを使って、私たちは言葉を大量に消費します。そこでは、言葉の多くが受動的に動きます。手紙や文章を書く。書くということは能動的な行為です。受け身の言葉のやり取りでは、言葉は重みとして心に止まることはありません。
福沢が手紙に書いた文明や国家、漱石が悩んだ人間の生き方。それらは言葉から掴んだものたちです。私は『福沢諭吉の手紙』を読んで、言葉の重みを意識させられました。生きた言葉。自己が自己を確立するための言葉を、自ら意識してゆかなければと思えるのです。ITのネットやマスメディアが張り巡らした網目の中に、自分の言葉を囚われないうちに。
慶應義塾大学 主催
第29回 オート・スカラシップ「小泉信三賞」
[
←back ] |



